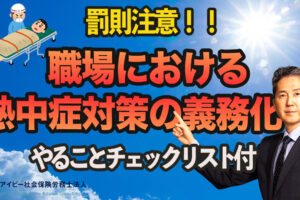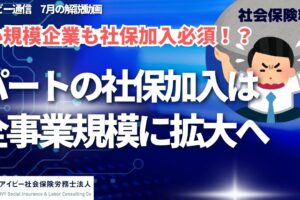1.はじめに
業務改善助成金は、生産性向上のための業務改善投資と賃金引上げに取り組む中小企業を支援する国の助成制度です。「賃上げだけでも大変なのに設備投資に振り向ける余力がない」という小規模事業者にとっては、特に活用するメリットが大きい助成金です。
しかしこの助成金は毎年のように要件が変更されます。前年と同じと考えて支給申請を行うと、要件を満たさずに不支給となる恐れもあります。
そこで今回は、令和7年度版の業務改善助成金を令和6年度版と比較しながら、改定の背景や助成金を活用する際の注意点について解説します。
なお、政府は2020年代に最低賃金を全国平均で1,500円水準まで引き上げる目標を掲げています。
激変緩和措置としてさまざまな支援策を用意していますが、「賃上げや生産性の向上は企業努力で実現する段階へ移行する」というシグナルとも読み取れる施策も打ち出しています。
助成金を活用できるうちに賃金原資を確保し、持続的に生産性を高める仕組みを整えることが、数年先の競争力を左右します。

2.令和7年度の変更点
2-1 事業場内最低賃金の基準となる労働者の雇用期間
令和6年度までは「雇入れ後3か月を経過」した労働者を事業場内最低賃金の基準労働者としていました。これが令和7年度は「6か月」に延長されました。
これにより、対象となる事業場や賃金引き上げ対象者、受給できる助成金額も変わってくる可能性がありますので注意が必要です。
2-2 みなし大企業の除外
中小企業の範囲を厳格化し、資本関係や役員兼任で大企業の影響下にある「みなし大企業」は助成対象外となりました。共同出資や系列企業間での資本関係がある場合は、申請前に組織図と株主構成を整理しておく必要があります。
2-3 引き上げ労働者数10人以上区分の取扱い
令和7年度も賃金引き上げ労働者数が「10人以上」の区分は特例事業者のみに適用されますが、助成上限(最大600万円)は維持されました。特例要件のうち賃金要件は区分が変更されています。
②物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
2-4 申請期間
令和6年度は申請期間が一本化されていてシンプルな設計でした。令和7年度は第1期(4月14日~6月13日)と第2期(6月14日~地域別最低賃金改定日前日)に分割され、各期の賃金引上げ期間も区切られています。背景には、最低賃金改定前に早期の賃上げを促し、物価高騰下でも従業員の可処分所得を確保する狙いがあります。第1期で申請をすると最低賃金改定日よりも大幅に前倒しで賃上げを行う必要があります。一方で第2期を選択する場合は、申請が集中することにより交付決定までに相当の時間がかかり、結果的に業務改善のタイミングが遅れてしまうリスクもあります。
2-5 特例事業者の助成率
令和6年度は、事業場内最低賃金が900円未満の場合に助成率を9/10、900円以上950円未満で4/5に引き上げる特例措置を講じていました。
令和7年度は最低賃金の全国平均が1,055円となったことを反映し、特例事業者の区分を1,000円未満の場合のみ、助成率も4/5に縮小する措置に変更しています。最高助成率が縮小した結果、自己負担比率は最大で10%から20%に増加しました。
2-6 事業主単位での600万円上限ルール
令和7年度は「事業主単位での上限600万円」が新設されました。複数事業場で同時に申請する場合でも、同一事業主単位で上限が600万円となることには注意しましょう。
変更点一覧
| 項目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 変更あり |
| 対象事業者 | 中小企業・小規模事業者(みなし大企業除く) | 中小企業・小規模事業者 | 〇 |
| 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差 | 50円以内 | 同左 | |
| 雇用条件 | 雇入れ後6か月以上 | 雇入れ後3か月以上 | 〇 |
| 賃金引き上げ額 | 30円以上引き上げ | 同左 | |
| 設備投資等の実施 | 生産性向上に資する設備投資 | 同左 | |
| 助成対象経費の支出期間 | 交付決定後~翌年1月31日まで | 同左 | |
| 助成率(原則) | 3/4(75%) | 同左 | |
| 助成率(賃金特例) | 1,000円未満:4/5(80%) | 900円以上950円未満:4/5(80%) 900円未満:9/10(90%) |
〇 |
| 物価高騰要件特例 | 物価高騰等により利益率が前年同月比3%ポイント低下 | 同左 | |
| 特例経費の拡充 | パソコン、タブレット、車両の特例対象あり | 同左 | |
| 申請回数 | 年1回まで | 同左 | |
| 同一年度内申請可能回数 | 1回限り | 同左 | |
| 不交付事由 | 解雇、賃金引下げ、労働保険未加入など | 同左 | |
| 交付申請受付期間 | 第1期:4/14~6/13 第2期:6/14~最賃改定前日 |
~令和6年12月27日(1期のみ) | 〇 |
| 助成額(最低) | 30万円 | 同左 | |
| 助成額(最高) | 事業主単位で600万円 | 事業場単位で600万円 | 〇 |
3.申請において注意すべき点
3-1 交付決定前着手の禁止は継続
助成率低下を受け、先行投資で導入コストを抑えたくなる場面もありますが、交付決定前に納品や支払いなどの導入行為を行うと不支給となります。必ず交付決定後に導入を行う必要があります。
3-2 事業場内最低賃金の引上げは一括で
複数回の分割引上げは令和6年度から認められていません。令和7年度も同様で、地域別最低賃金発効日の前日までに一気に改定する必要があります。引上げ幅と発効日を就業規則に明記して所轄労働基準監督に届出が必要です。
3-3 就業規則と賃金台帳の整合
助成金の支給申請時には、改定後賃金を記載した賃金台帳と就業規則または賃金規程が必須添付書類です。就業規則の内容と実際に支給した賃金が一致している必要があります。特に月給を時間給に換算する際、1円未満の端数が生じる場合には、四捨五入処理する必要があります。勝手に切り上げてしまうと申請した結果、賃金引上げ額を満たさず不支給となる可能性もありますので注意してください。
4.まとめ
令和7年度の業務改善助成金は、早期賃上げを促す2期制、1,000円を境とした助成率の再編、対象労働者の要件厳格化等、複数の改定が行われています。一見ハードルが上がったようにも映りますが、物価高騰特例や600万円上限は維持されており、制度を使いこなせば賃上げ費用の7~8割を補填できる可能性があります。

経営者が今取るべきアクション
(A)直近6か月超勤務の従業員リストを作成し、引上げ幅別のコース試算を実施
(B)第1期、第2期のどちらで申請するかメリット・デメリットを考慮して検討し、設備投資見積もりと資金計画を確定
(C)物価高騰要件の該当有無を確認し、特例による対象経費の投資可否を判断
これらを踏まえ、厚生労働省が公開している最新情報を常にチェックしてください。
本記事をチェックリストとして活用し、制度改定をビジネスチャンスへと転換してください。
最後に、助成金はあくまで成長投資を促す補助線であり、申請が目的化しては本末転倒です。
業務改善助成金は、今後も数年は継続する可能性もありますが、助成金に頼らずとも自走できるよう、今後数年の長期的な視点で自社の賃金方針と業務改善戦略を見直すことが重要となります。
※ 本記事は令和7年4月現在で厚生労働省が公開している情報を元にしています。申請にあたっては本記事以外にも確認すべき点が多数あります。助成金は年度途中でも変更されることがたびたびありますので、自社申請する場合は必ず公開されている最新のパンフレット、交付要領、交付要綱を入念にチェックする必要があります。