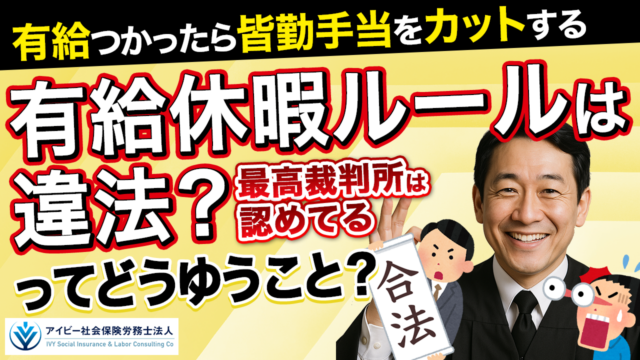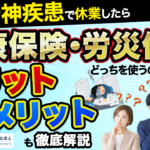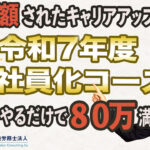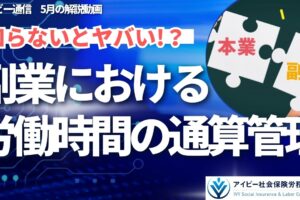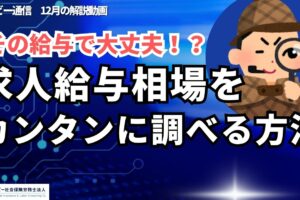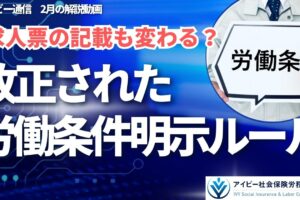1.はじめに
サービス業を中心に支給している企業も多い皆勤手当。会社を休まなければ支給される手当ですが、年次有給休暇を取得した場合でも「皆勤」と認められるのでしょうか?もし有給の取得を理由に皆勤手当がカットされるなら、それは違法ではないのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
本記事では、皆勤手当と年次有給休暇に関する最高裁判所の判例を交えながら、どのようなケースが適法または違法となるのかを解説します。企業が実務的に留意すべき点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

2.皆勤手当とは
皆勤手当は、労働基準法で支給が義務づけられる賃金ではなく、あくまでも企業が何らかの目的(趣旨)をもって支給する任意の賃金です。その目的や趣旨は、出勤成績が優良な労働者に対して、その勤務態度や労働意欲を評価・奨励するためというのが一般的でしょう。そのため、賃金計算期間(通常は1か月間)において無遅刻・無欠勤・無早退など、すべての所定労働日に皆勤した労働者に対して支給されます。
では、欠勤ではなく年次有給休暇を使って休んだ場合はどうでしょうか。労働基準法第134条(現在は附則第136条)には、以下の規定があります。
この規定に当然違反するのではないか、と疑問に思いますよね。
3.年休取得を理由に皆勤手当をカットするのは合法!?
年次有給休暇の取得を理由に支給対象外とする運用を「違法ではない」と判断した最高裁判例があるのをご存知でしょうか。「沼津交通事件」(平成5年6月25日・最高裁第二小法廷判決)です。
この裁判では「年次有給休暇を取得した労働者に皆勤手当を不支給とする措置」が公序良俗違反として無効になるかが争点となりました。以下に判決のポイントを整理します。

3-1.判決の要旨
年次有給休暇を取得した労働者に対し、皆勤手当を減額・不支給とする制度が、労働基準法第39条および第134条に違反し、公序良俗に反して無効かどうかが争われました。

3-2.労基法134条は「努力義務」規定である
最高裁判所は、年次有給休暇取得者に対する不利益取扱いを「しないようにしなければならない」と定めた同条は、使用者への努力義務を課すにとどまり、私法上の効力を直接否定する強行規定ではないと判断しました。つまり、企業には「年次有給休暇を取得したことを理由にして労働者を不利益に扱わないように努める義務がある。しかし、それに反した取り扱いを行ったからといって、ただちに企業が決めたルールが否定されるわけではない、という立場をとりました。
3-3.有給取得抑止力の程度と公序違反の判断基準
年次有給休暇の取得に伴う経済的不利益が、労働者の権利行使を実質的に抑制するような場合には、公序良俗に反して無効となる可能性があります。しかし、すべてが直ちに無効になるわけではありません。最高裁は以下の諸事情を総合的に考慮し、皆勤手当を不支給とすることが公序良俗に反しないと判断しました。
- 業種(タクシー)特有の事情: 出勤率の確保が経営上極めて重要であること
- 支給額の少額性: 支給されていた皆勤手当は月額最大4,100円であり、総給与に対する割合が1.85%と少額であること
- 抑止力の小ささ: 年次有給休暇取得による手当不支給が、取得を実質的に抑制するほどの効果を持たず、一般的な取得抑制を目的としていると見られないこと

3-4.解釈上の意義
この最高裁判決は、労働基準法134条を訓示的規定(努力義務)と位置づけ、公序良俗違反の有無を個別具体的に判断する立場を採用しました。これは、前年の最高裁判決「エス・ウント・エー事件」(平成4年2月18日・最高裁第三小法廷判決)が年次有給休暇取得に基づく賞与減額を否定したのとは異なる解釈を示しており、労働者の権利保護だけでなく、経営上の合理性との調和を重視した判断である点が注目されました。
3-5.実務への影響
企業は年次有給休暇取得者への不利益取扱いを可能な限り避けるべきです。しかし、仮に経済的不利益があったとしても、その不利益が年次有給休暇の取得を実質的に抑止する効力が小さく、手当制度の趣旨が正当かつ限定的であれば、手当の減額や不支給が有効と認められる余地があることを、この判決は示しました。
4.実務上の留意点
最高裁が「皆勤手当のカットを認めた」という判決があったからといって、年次有給休暇を取得した従業員の皆勤手当を一律にカットしても問題ない、と安易に判断するのは危険です。この判決は、皆勤手当のカットといった不利益取扱いを一律に有効と認めたものではないためです。実務への適用にあたっては、以下の表に示すように、年次有給休暇取得への「抑止力の程度」、皆勤手当の「金額や給与総額に対する割合」、皆勤手当制度の「趣旨・運用状況」などを総合的に考慮し、個別具体的な判断が求められます。
| 区分 | 判断要素 | 具体例 |
|
違法(無効)となる
可能性がある場合 |
・皆勤手当の額が高額で、収入に与える影響が大きい | 月給の5%以上等、生活費への影響が大きいと認められる額の場合 |
| ・制度が年休取得を事実上抑制する実態となっている | 年休を取得すると大きく収入が減るため、取得しない社員が多い状態 | |
| ・皆勤手当の趣旨が「年休取得抑制」と解される | 「年休を取ると皆勤手当は出さない」と明言している | |
| ・年休取得者を明確に差別し、懲罰的要素がある | 年休取得者を不誠実・非協力的とみなす旨の運用や評価と結び付けている | |
|
違法ではない(有効)と
される可能性がある場合 |
・皆勤手当の金額がごく少額で、抑止効果が軽微 | 月額数千円程度、月収に対する割合が1〜2%以下 |
| ・制度趣旨が業務運営上の合理的必要性に基づいている | シフト制業務において、急な欠勤防止や代替要員の確保困難などの事情がある | |
| ・皆勤手当が「報奨金的」性格を有し、欠勤全般を対象にしている | 病欠・私傷病・遅刻・年休を問わず、出勤実績のみで支給判断している場合 | |
| ・年休取得率が高く、実際に制度が抑止力を持っていない実態がある | 年休取得率が高く、手当の有無にかかわらず取得できている現場環境 |
5.企業対応
皆勤手当は企業が任意で支給する賃金であり、年次有給休暇取得を理由に減額・不支給とすることが直ちに違法とは限りません。本記事で解説した最高裁判所の判例(沼津交通事件)が示すように、手当の金額や制度の趣旨、年休取得への抑止力などを総合的に判断し、公序良俗に反するかどうかが個別に判断されます。
企業は手当の支給条件を明確にしたうえで、業務運営とのバランスを考慮しながら、合理的なルールのもと、従業員が安心して有給を取得できる環境を整える必要があります。企業側がこの判例を誤って解釈し、年次有給休暇の取得を実質的に妨げるような運用を行った場合、従業員との間でトラブルや短期離職のようなデメリットが発生するリスクがあります。
この判例が示したのは、あくまで個別の事案における判断であり、すべての皆勤手当の減額・不支給が適法となるわけではないという点には注意が必要です。特に、皆勤手当の支給額が高額であったり、その減額・不支給が従業員の年次有給休暇取得意欲を著しく阻害するような実態がある場合には、監督署からの指導対象となったり、公序良俗に反するルールとして企業イメージを低下させる可能性もあります。企業としては、労働基準法第134条の努力義務を最大限に尊重すべきです。皆勤手当の制度を見直す際には、社会保険労務士のような専門家と相談しながら、年次有給休暇の取得を妨げないような設計と運用を心がける必要があります。

6.まとめ
今回は皆勤手当と年次有給休暇に関する最高裁判所の判例を交えながら、どのようなケースが適法または違法となるのかを解説してきました。皆勤手当は企業が任意で支給する賃金であり、年次有給休暇取得を理由に減額・不支給とすることが直ちに違法とは限りません。しかし、今回ご紹介した最高裁判例はあくまで個別の事案における判断であり、皆勤手当の金額や制度の趣旨、年休取得への抑止力などを総合的に考慮し、公序良俗に反するかどうかが個別に判断されます。
企業は従業員が安心して有給を取得できるよう、手当の支給条件を明確にし、労働基準法第134条の努力義務を最大限に尊重した制度設計と運用を心がけることが重要です。