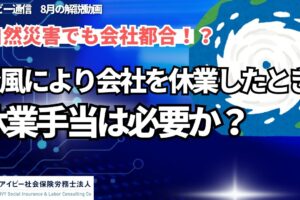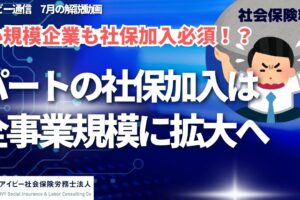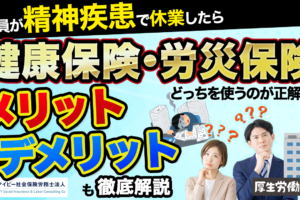1.はじめに
ここ数年、弊所の顧問先でも退職代行サービスから退職通知が届いた、と相談を受けるケースが増えています。退職代行サービスが広く認知されるようになったのは2018年頃からですが、ここ数年では特に若年層を中心に利用が急増している様子がみられます。
就職情報サイトのマイナビが2024年10月に発表した「退職代行サービスに関する調査レポート(企業・個人)」によれば、直近1年間で退職した20代の18.6%が退職代行を利用しており、30代〜40代も17%以上が利用している状況で、すでに若年層では一般化している印象です
この記事では企業側の視点で、退職代行サービスから退職通知を受けた場合の対応、そして退職代行サービスを使った退職を防止する方法、そもそもミスマッチ退職を出さない方法について分かりやすく解説していきます。

2.退職代行サービスとは
退職代行サービスとは、労働者が自ら退職の意思を会社に伝えることが困難な場合に、その手続きを第三者が代行するサービスです。特に「上司が怖くて言い出せない」「辞意を伝えても受理されない」といった心理的なハードルを感じやすい若年層を中心に利用が広がっています。
退職代行サービス事業者の形態にはいくつかの類型があり、それぞれ法的な対応範囲が異なります。
2-1.弁護士型
弁護士が運営する退職代行サービスでは、退職の意思伝達だけでなく、未払い残業代の請求や損害賠償に関する交渉など、法律上の代理行為を含む対応が可能です。法的知識を備えた専門家による対応のため、より複雑な退職事案に対応可能という特徴があります。一方で、費用は高めになる傾向があります。
2-2.労働組合型
労働組合が提供する退職代行サービスは、団体交渉権を根拠に、会社との交渉や連絡を行うことができます。組合の構成員である労働者の代理として交渉を行うため、労働条件や退職時の手続きに関する協議も一定範囲で可能です。ただし、あくまで組合員としての交渉権限に基づくものであり、法的代理権のある弁護士とは異なります
2-3.いずれにも該当しない退職代行サービス
民間企業によるサービスで、弁護士資格や労働組合の地位を持たない業者も数多く存在します。この場合、退職の意思を「伝える」行為は代行できますが、会社との交渉や法的な主張、請求は行えません。利用者にとっては低価格で手軽に使えるためもっとも利用者が多い類型ですが、企業側は法的な交渉や請求には応じる義務がありません。
企業側としては連絡元の退職代行サービス事業者の法的立場がどの類型となるのか見極めることも重要となります。
3.企業として対応すべきこと
退職代行サービスから退職の連絡があった場合、企業としては冷静かつ法的根拠にもとづいた対応をとる必要があります。代行業者の類型や連絡内容に応じて、対応方法には違いがあります。共通して重要なのは「退職の意思を尊重しつつ、会社として必要な手続きを着実に進めること」です。一方で、対応を誤ると法的リスクを招く可能性もあります。ここからは、企業が「すべきこと」と「すべきではないこと」を実務項目ごとに整理します。
3-1.本人確認
退職代行サービスから連絡があった場合、まず確認すべきは本当に本人の意思による依頼かどうかです。企業としては、退職の意思表示が代理人によるものだとしても、本人の意思に基づいていることが明らかでなければ対応を保留することが妥当です。本人からの署名入りの退職届や、本人確認書類の提出を求め、意思確認の証拠を残しておくことが重要です。
3-2.有期契約労働者の場合
有期契約労働者が契約期間中に退職を希望する場合、原則として契約期間満了まで労務提供義務があるため、会社としては一方的な退職の申出をただちに受け入れる必要はありません。(労働契約法第17条)ただし、やむを得ない事由(ハラスメントや健康悪化など)がある場合は中途解約が認められることもあるため、具体的な事情を確認して判断することが求められます。いずれにせよ、雇用契約書や就業規則に契約期間中の退職についてどのように規定しているのかをチェックする必要があります。
3-3.引継ぎ義務の履行請求
退職予定者には、就業規則や労働契約上の義務として業務の引継ぎを行う責任があります。退職するまで雇用契約は有効に存続している訳ですから、退職代行を通じての退職であってもこの義務が免除されるわけではありません。ただし、本人と直接連絡が取れない場合や、引継ぎが不可能な状況もあるため、書面やデータによる間接的な引継ぎの指示を行うなど、現実的な対応策を検討する必要があります。なお、無断欠勤や引継ぎ義務を放棄した結果、会社に損害が生じた場合は、就業規則に基づいて懲戒処分を行ったり、発生した損害について労働者に賠償を求めることも理論的には可能です。
3-4.有休処理
退職にあたって年次有給休暇の残日数がある場合、労働者はその取得を申し出ることで原則として休暇の消化が可能です。企業側は事業運営に著しい支障がある場合は時季変更権の行使も可能ですが、退職時には変更できる時期が事実上限定されるため、実務上は退職日までの有休消化が認められるケースが多いです。退職日と有休消化期間の整合性を確認し、社内手続きを適切に進めることが重要です。
3-5.社宅・社員寮
社宅や社員寮を貸与している場合、退職に伴い労働者は契約終了後の明渡し義務が発生します。契約書、社宅利用誓約書、社宅利用管理規程等をもとに、退職日以降の退去期限を明確に伝えることが重要です。トラブル防止のためには、原状回復や鍵の返却等の具体的な手続きも文書で案内するのが良いでしょう。
3-6.制服等の貸与物
制服や社員証、備品など会社から貸与している物品については、退職時に速やかに返却を求めることができます。返却が困難な場合や連絡が取れない場合には、郵送による返却方法を案内するなど、合理的な対応策を提示することが重要です。返却がないまま私的使用されるとトラブルに発展する恐れがあるため、返却期限や未返却時の対応についても明示しておくことが望まれます。
3-7.賞与
賞与は就業規則や賃金規程に基づいて支給の有無や算定基準が判断されます。退職者に対する賞与支給についても、「在籍していることを支給要件とする」旨が規程に明記されていれば、支給しない対応は原則として有効です。トラブル防止のためには、賞与支給に関するルールを就業規則等に明文化し、事前に周知しておくことが重要です。
3-8.退職金
退職金の支給は法的義務ではありませんが、制度の有無や支給条件は会社の退職金規程に基づいて判断されます。規程で勤続年数や退職理由による支給要件が定められている場合には、その要件に従って支給の有無や金額を決定します。
アイビー社会保険労務士法人では、上記の労務リスクを予め想定し、労務リスクを低減できる就業規則の整備を行っています。特に業務の引継ぎ義務を明記し、違反した場合の対応についても規定を設けることにより、無断退職や一方的な退職による業務混乱への抑止効果を持たせています。こうした規定を設けることで、退職者の行動に一定の責任を求めるとともに、在職中の義務を果たす意識づけにもつながり、企業側の労務リスクを軽減します。円滑な退職手続を促すためにも、きちんと就業規則に明文化しておくことは特に重要です。

4.すべきではないこと
退職代行サービスからの連絡に直面した際、企業として冷静な対応が求められる一方で、不用意な行動がトラブルの拡大や法的リスクにつながることもあります。感情的な対応や、適切な手続きを踏まない対応は、かえって企業の信頼を損ねる原因となりかねません。ここでは、企業として「してはならない対応」について、実務上注意すべき点を整理します。
4-1.無視する
退職代行サービスからの連絡を無視することは、トラブルの長期化や労使紛争の火種となるリスクがあります。たとえ代行業者が非弁行為に該当する可能性がある場合でも、退職申出が本人の自由意思に基づくものであれば、企業は誠実に対応すべき法的義務があります。連絡を受けた場合は、内容を精査した上で、本人の意思確認や必要な手続きの案内を行うなど、事務的に対応することが重要です。
4-2.ムリに本人と連絡を取る
退職代行サービスを通じて退職の意思が示された場合、会社が執拗に本人へ直接連絡を取ろうとしたり、直接連絡を強要する行為が行きすぎると、ハラスメントと受け取られる可能性があるため、慎重な対応が求められます。ただし、先述したとおり、雇用関係が法的に終了していない段階では、会社には労働契約に基づく連絡・指示の権限があります。そのため、業務引継ぎや貸与物返却、就業規則を根拠とする必要な事項については、事務的・適切な範囲での連絡は可能です。
その際は、感情的な言動や執拗な連絡を避け、書面やメールなど記録が残る手段で、必要最小限の連絡を行うことが望ましく、本人の状況や連絡手段の選定には配慮が必要です。
5.退職時のルールは就業規則で
5-1.記載しておくべき退職時の手続き
退職に関する混乱やトラブルを防ぐために、就業規則には退職時の手続きを明確に定めておくことが不可欠です。具体的には、退職の申出方法と期限、引継ぎ義務、貸与物の返却、最終出勤日や退職日の取り扱いなどを記載し、従業員にあらかじめ周知しておきます。こうしたルールが整備されていれば、退職代行を通じた連絡にも冷静に対応でき、法的根拠に基づく対応が可能になります。
5-2.最終給与の現金払い
退職者が退職代行を通じて一方的に連絡を断つことは、事業運営に重大な支障をきたす場合もあります。そのため、就業規則に定めた退職手続によらずに退職申出を行った場合は、最終給与を現金で支払う旨を就業規則に定めておくことも有効です。これは労働基準法第24条に基づく賃金支払原則を前提としつつ、退職代行の安易な利用に一定の抑止効果を持たせることができます。実際にやるかどうかは個々の企業判断となりますが、現金支払いする場合は、本人確認や受領記録の保存を徹底し、法的トラブルを防止する対応が必要です。なお、労働者が現金受取に来ない場合、会社はいつでも渡せるように賃金債権の時効となる3年間は保管しておく必要があります。そのような管理コストがかかる方法でもあることには留意が必要です。
6.問題は退職代行サービスではなく離職の原因
6-1.なぜ多くの人が退職代行サービスを使うのか
退職代行サービスの利用が広がる背景には、上司に直接退職を伝えにくい職場風土や、退職を申し出ても引き止められることへの不安があります。特に若年層では、人間関係のストレスや精神的な負担を避けたいという心理が強く、第三者を介して円滑に退職したいと考える傾向が見られます。つまり、問題の本質は退職代行そのものではなく、社員が安心して辞意を伝えられない職場環境や企業文化にあるともいえます。

6-2.組織としてハラスメント体質がないかチェック
離職理由はさまざまですが、上司からの高圧的な言動や無自覚なパワハラが潜在的に存在しているケースは少なくありません。社員が直接辞意を伝えられない背景には、「言えば何をされるか分からない」「どうせ受け入れてもらえない」といった不信感や恐怖心があることも多く、これは組織としてのハラスメント体質の表れです。定期的に社内ハラスメントアンケートや個別面談などで風土を点検し、問題があれば早期に是正する体制を整えることが、信頼される職場づくりの第一歩です。
6-3.離職時にとりたい退職理由アンケート
離職の原因を正しく把握するためには、退職者から退職理由を聞き取るアンケートの実施が効果的です。形式的な質問ではなく、自由記述欄や複数選択肢を設けることで、本音に近い意見を収集できます。特に退職代行を利用された場合でも、郵送やメールで回収できる仕組みを整えておくことで、職場風土改善のヒントを得ることができるケースもあります。データを蓄積し、傾向を分析することで、離職防止につながる具体的な対策が打ちやすくなります。
6-4.退職理由ワースト3を優先的に対処する
離職防止策を講じるうえでは、実際に多くの退職者が挙げる理由に優先的に対応すべきです。特に20代前半では、「賃金」「労働時間・休日などの労働条件」「人間関係」が退職理由の上位を占めており、これらに優先的、かつ具体的に手を打つことが、若手社員の定着に直結します。制度面の見直しだけでなく、対話の機会を増やし、現場の不満を吸い上げる仕組みを持つことが、従業員定着率の改善につながります。特に賃金、労働時間・休日といった労働条件面は、問題があることは認識していても、社内だけでは現実的な解決に向かわないケースが多いです。そんなときには外部の専門家を入れ、期間を決めてプロジェクト形式で集中的に対応するのが解決の近道です。
7.採用する前の段階でミスマッチを防ぐ
7-1.会社の情報はなるべく多くオープンに
採用時のミスマッチを防ぐためには、採用する前段階で会社の実態や働き方、社内の雰囲気などの情報を可能な限り開示することが重要です。給与や勤務時間といった条件面だけでなく、職場文化や経営者の考え方、5年後、10年後、20年後といった中長期的なキャリアの現実なども含めて丁寧に説明することで、入社後のギャップを減らせます。情報を隠さず伝える姿勢は、応募者の信頼感を高め、定着率の向上に良い影響を与えます。
7-2.問題があるなら改善策も含めて開示
採用時に自社の課題を隠すのではなく、現状の問題点とそれに対する改善策をあわせて開示することで、誠実な企業姿勢として信頼を得るきっかけになる場合があります。たとえば「今は残業が多いが外部コンサルを入れて削減に向けた取り組みを進めている」など、課題と向き合っている姿勢を示すことで、共感や理解を得やすくなり、入社前の期待値と入社後のギャップによる早期離職の防止にもつながります。
7-3.キラキラ職場を謳った採用ページは要注意
最近自社のホームページに採用ページを追加する企業が増えています。ただ、採用競争が激化する中で、「働きやすさ」「自由な社風」などを強調しすぎた“キラキラ職場”を演出する採用ページが増えており、実態とかけ離れた情報発信は入社後の失望や早期離職を招くリスクがあります。過度な理想像ではなく、現実を正しく伝えた上で自社の魅力を伝えることが、採用の質と定着率を高める上で重要となります。採用は企業の“信用取引”であることを常に意識すべきです。
8.ホワイトなだけが良い職場でもない
8-1.仕事のやりがいや企業の存在理由を再定義する
制度や待遇が整った「ホワイトな職場」であっても、仕事にやりがいを感じられなければ、社員のモチベーションや定着にはつながりません。単なる業務の遂行ではなく、自分の仕事が誰にどう役立っているのか、成長や達成感を得られているかといった視点で、仕事の「やりがい」や、もっというと企業の上位概念であるミッション、ミジョン、バリューを再定義することを今一度検討することも重要です。仕事の意味づけや目標設定の工夫が、社員の主体性と定着力を高める鍵となります。
8-2.衛生要因だけではなく動機付け要因を刺激する
給与や労働時間、福利厚生などの衛生要因は「不満を防ぐ」ために必要な条件ですが、それだけでは社員の意欲や定着を高めることはできません。重要なのは、達成感・承認・成長機会といった「動機付け要因」を意識的に整備し、社員が前向きに働ける環境をつくることです。制度とあわせて、仕事への誇りや役割意識を育てる取り組みが、定着につながる職場づくりに不可欠です。
8-3.突然の退職をふせぐには
社員の突然の退職は、業務の停滞や他の社員への悪影響を招く重大なリスクです。これを防ぐには、退職に至る前段階での不満や兆候に早期に気づき、適切に対応する仕組みが必要です。
また、就業規則に基づいた明確な退職手続きを整えておくことで、手続きの流れが分かりやすくなり、突発的な離職の抑止にもつながります。
8-4.連鎖退職防止のために
一人の退職が引き金となり、他の社員にも不満や不安が広がることで連鎖的な退職が起こるリスクがあります。これを防ぐには、退職後の業務フォロー体制を迅速に整えるとともに、残る社員への丁寧な説明やケアを行い、不安の払拭に努めることが重要です。さらに、職場の不満要因を放置せず、改善に取り組む姿勢を明示することが、信頼の維持と離職拡大の抑止につながります。

10.まとめ
退職代行サービスの利用が広がる中で、企業に求められるのは、冷静かつ制度に基づいた実務対応です。退職手続のルールを就業規則に明確に定め、引継ぎや貸与物返却、最終給与の支払い方法まで具体的に整備しておくことが、トラブルの抑止につながります。また、退職代行の背景には職場環境や人間関係への不満があることが多く、原因の本質に向き合う姿勢が必要です。
採用のミスマッチを防止し、定着率を高めるためには、採用時の情報開示、定着を促す仕組みづくりといった、総合的かつ継続的な労働条件の改善、見直しが求められます。
今回の記事でご紹介した、「社内ハラスメントアンケート」や「退職理由アンケート」の加工可能なひな形を無料でお渡ししています。ご興味あるかたは、お問い合わせページから「ひな形希望」と書いてお問い合わせください。